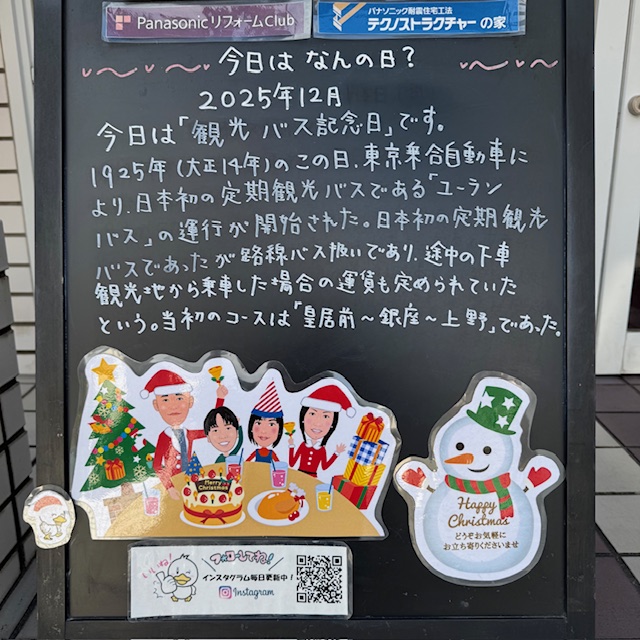1月8日は「イヤホンの日」
今日は「イヤホンの日」です。
どこにでも持ち運べて、
いつでも気軽に音楽を聴けるイヤホンの普及目的として、
イヤホンの総合情報サイトである「イヤホンナビ」が制定しました。
日付の由来は1と8で「イヤホン」の語呂合わせからきています。
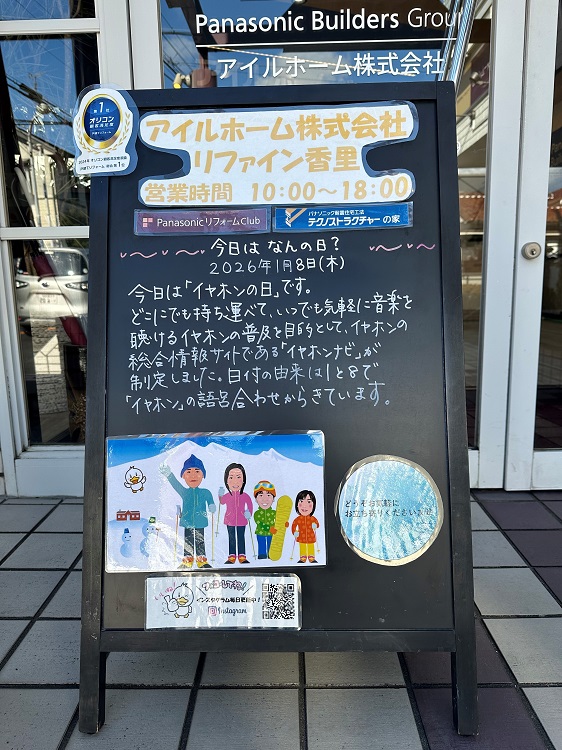
今日は「イヤホンの日」です。
どこにでも持ち運べて、
いつでも気軽に音楽を聴けるイヤホンの普及目的として、
イヤホンの総合情報サイトである「イヤホンナビ」が制定しました。
日付の由来は1と8で「イヤホン」の語呂合わせからきています。
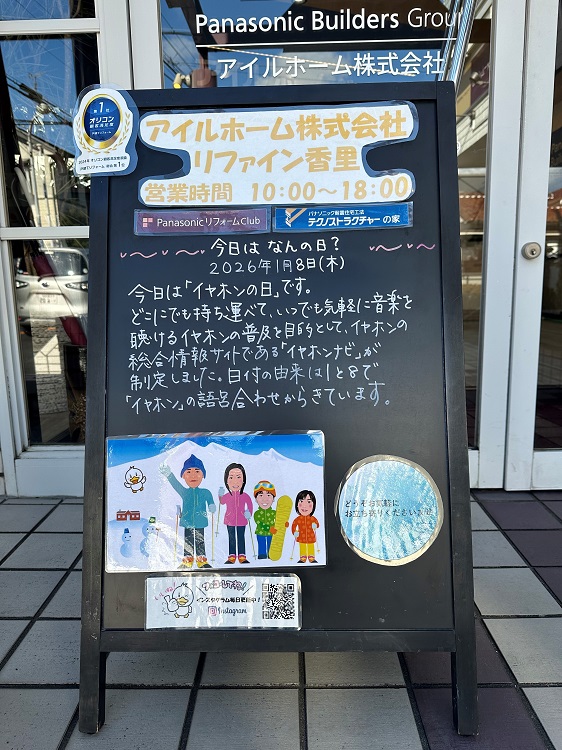
今日は「ケーキの日」です。
1897年(明治12年)のこの日、東京・上野の風月堂が日本初のケーキの宣伝したとされる。
東京日日新聞に掲載された広告の内容は「文化は日々開けていき、すべてのものが西洋風になってきますが、ただ<西洋菓子(ケーキ)>を作っている人はいません。そこで当店では外国から職人を雇ってケーキをつくり博覧会へ出品したところ大好評でした。ぜひご賞味ください。」というものだった。
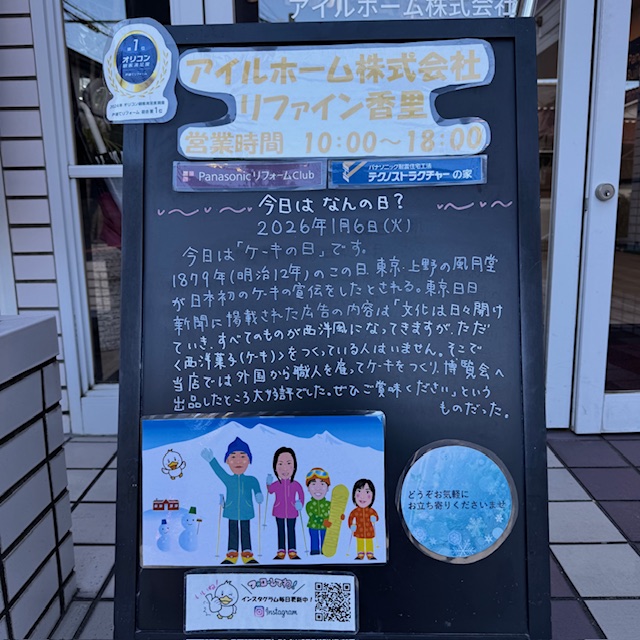
今日は「浅草仲見世記念日」です。
1885年(明治18年)のこの日、東京・浅草の「仲見世」が新装開業した。
浅草仲見世は雷門から浅草寺へと続く古い商店街で、日本で最も古い商店街の一つである。
現在、商店が立ち並ぶ通りは「仲見世通り」と呼ばれ、長さが約250mで東側に54店、西側に35店、合計89の店舗がある。
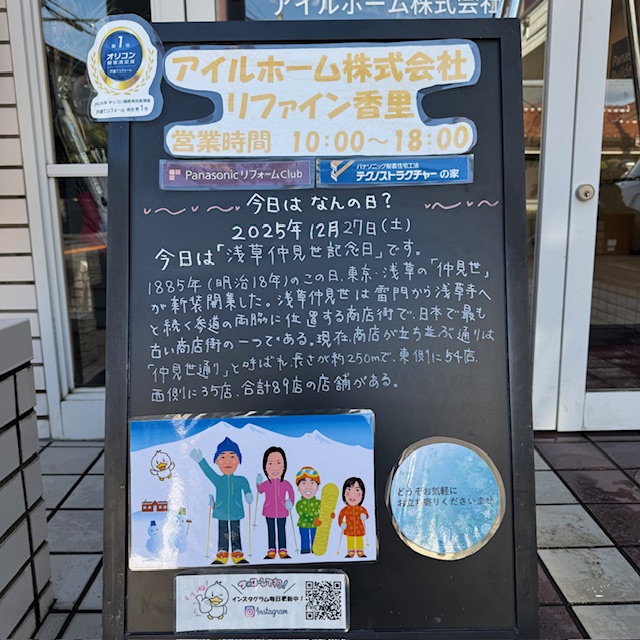
今日は「東京タワー完成の日」です。
1958年(昭和33年)のこの日、東京・芝公園に「東京タワー」完成し、完工式が行われた。
高さ333mでフランス・パリのエッフェル塔の312mより高く当時世界一の高さの建造物となった。
東京タワーの正式名称は「日本電波塔」で東京のシンボル観光名所となっている。
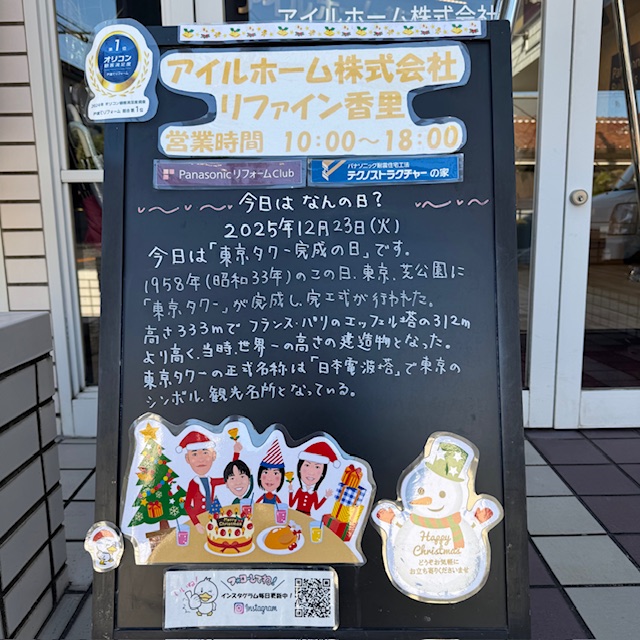
今日は「スープの日」です。
日本のスープ業界の発展を目指して1980年にスープ製造企業などにより結成された日本スープ協会が制定。
日付は温かいスープをより美味しくて感じることができる「冬」であり「いつ(12)もフーフー(22)とスープをいただく」と読む語呂合わせから12月22日とした。
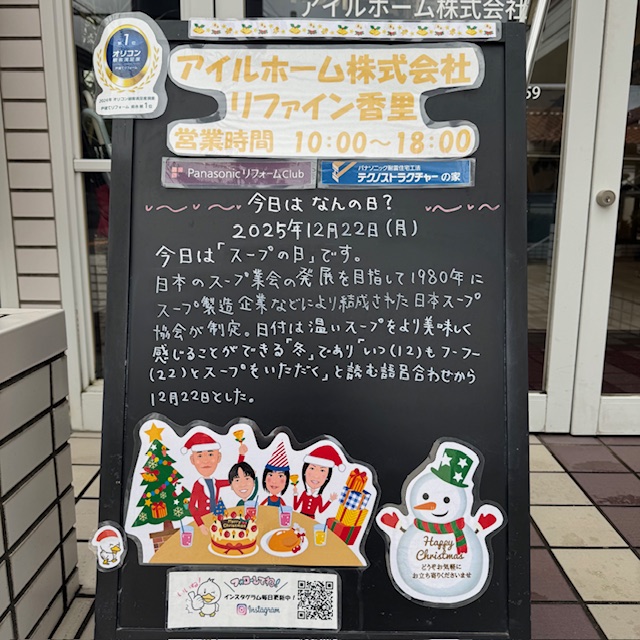
今日は「大吉日」です。
暦を元にした占いや風水学では、
天赦日の為すこと全てに恩恵を授かる極上の吉日(年間5~6日)と、
一粒万倍日の何か始めた行いが成果として実を結びやすく
金運にも良い(月ごとに4~6日)がそれぞれありますが、
2つの重なる日が本日で縁起の良い大吉日となっています。
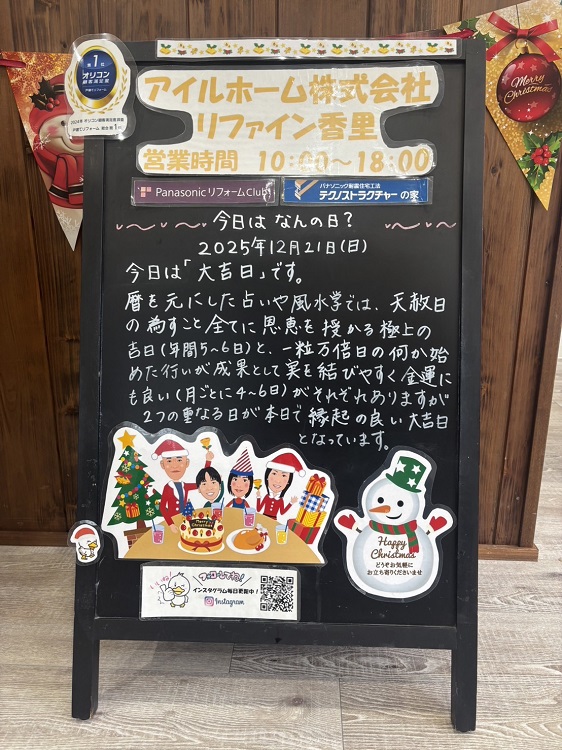
今日は「デパート開業の日」です。
1904年(明治37年)のこの日、東京日本橋の「三井呉服店」が「三越呉服店」と改称し、日本で初めてのデパート形式の営業を開始した。
当時の三越呉服店は2階建てで日本商家の古風を残したものだった。
「三越」の名称は三井家の「三井」と創業時の「越後屋」に由来する。
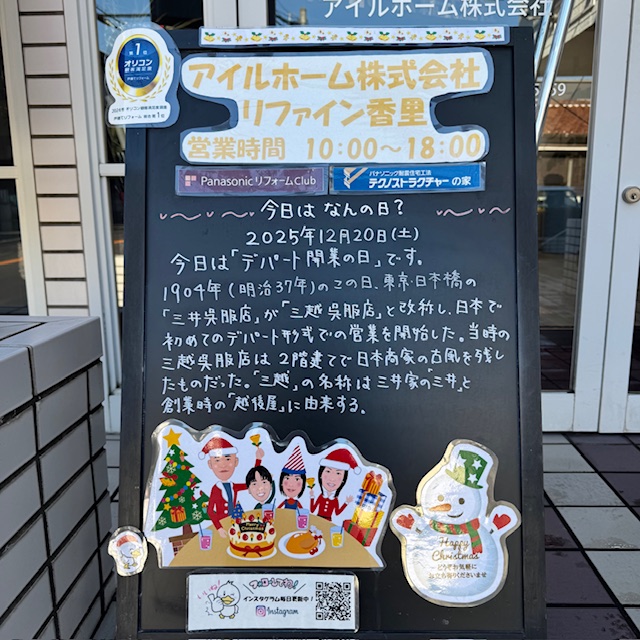
1910年(明治43年)のこの日、東京・代々木錬兵場(現:代々木公園)で陸軍軍人(工兵大尉)徳川 好敏(とくがわ よしとし 1884-1963)が日本人初飛行に成功した。
飛行機はフランス製のアンリ・ファルマン複葉機で飛行時間は4分・最高高度は700m・飛行距離は3000mであった。
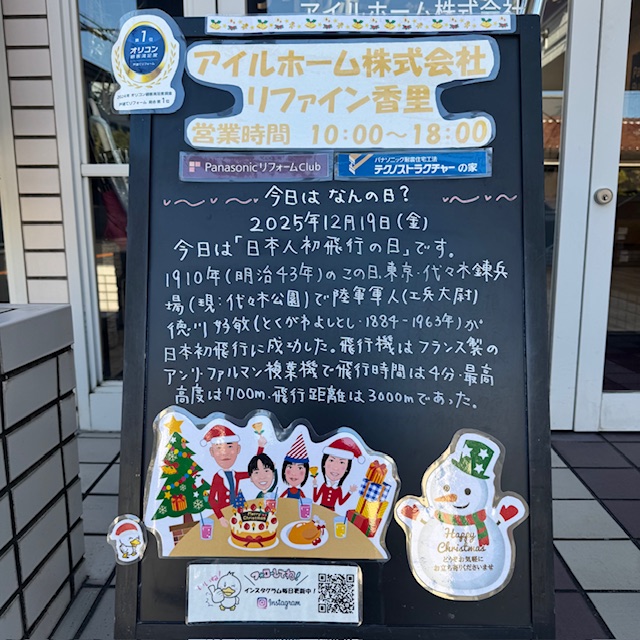
今日は「電話創業の日」です。
1890年(明治23年)のこの日、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始し千代田区に設置された電話交換局が営業を始めた。
加入電話は東京155台、横浜44台、電話交換手は女子7人、夜間専門の男子2人が対応した。
当時の電話料金は定額料金で東京が40円、横浜35円。
今の値段にすれば40円は24万円くらいに相当し当時の電話はとても高価なサービスだった。
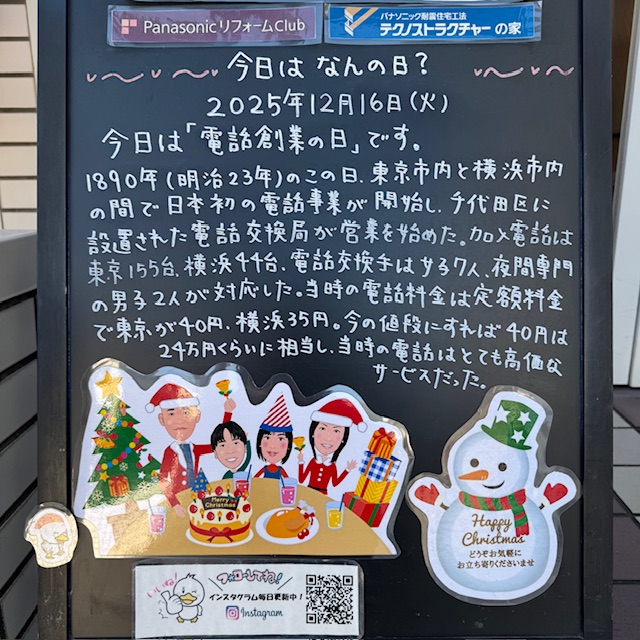
今日は「観光バス記念日」です。
1925年(大正14年)のこの日、東京乗合自動車により日本初の定期観光バスである「ユーランバス」が開始された。
日本初の定期観光バスであったが路線バス扱いであり、途中の下車観光地から乗車した場合の運賃も定められていた。
当初のコースは「皇居前~銀座~上野」であった。